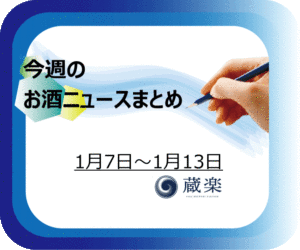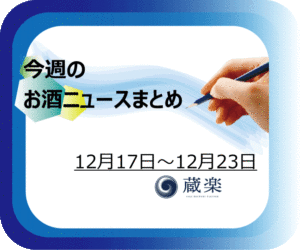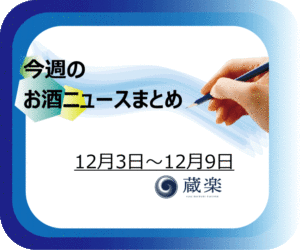一部の方は先週からお盆休みに入られたそうですね。
一方で、酒蔵の売店では、帰省と観光で賑わいを見せているところもあるそうです。
先週末は休みを利用して、茨城県ひたちなか市にある酒列磯前神社(さかつらいそさきじんじゃ)へ行ってまいりました。
その名のとおり「酒」の字を冠し、お酒の神様である少彦名命(スクナヒコナ)を祀っております。
また、大洗にある大洗磯前神社の兄弟神社でもあります。
境内には不思議な力強い空気が満ちており、しっかりとパワーをいただきました。
改めて酒造業界への貢献していきたい気持ちが高まり、誠心誠意努力していく思いを込めてお祈りしました。
それでは今週の日本酒NEWSです🍶✨
🍶トピック🍶
①.白鶴酒造、神戸市に新工場 26年秋完成
②.八戸酒造、オリジナル酒造好適米を開発
③.400回洗える酒器用ヒノキ升
①.白鶴酒造、神戸市に新工場 26年秋完成(詳細はコチラ)
白鶴酒造は日本酒の新工場の建設を始めたと発表しました。完成は2026年10月末を見込んでいます。築73年が経過した季節醸造工場の後継施設として、純米酒、吟醸酒といった特定名称酒を通年で醸造する予定です。
新工場は鉄筋コンクリート造り2階建てで、延べ床面積は2425平方メートル。年間で1100キロリットルの生産能力を持たせます。同社が醸造工場を新設するのは、1964年完成の本店三号工場以来、約60年ぶりです。
これまで同酒造の特定名称酒は1952年完成の本店二号蔵工場を中心に造っていました。冬場には全国から訪れる職人らが寝泊まりしながら醸造していましたが、職人の高齢化や人手不足を踏まえ、社員だけで通年醸造できる設備の新設を決めました。なお、本店二号蔵工場は2025年秋から26年春にかけての仕込みを最後に解体となります。
新工場の製造能力は、年間1100リットル(=約6,000石)ということで、さすがの白鶴酒造さんの投資規模です。今回の投資により、社員だけで通年醸造をできるようになるため、品質の安定性や稼働率の向上が期待できそうですね◎
②.八戸酒造、オリジナル酒造好適米を開発(詳細はコチラ)
八戸市の八戸酒造は同社オリジナルの酒造好適米を開発し、その酒米を使用した「陸奥八仙 創業250周年記念ボトル」を販売しています。記念ボトルのアルコール度数は15度。華やかな香りとすっきりした仕上がりです。720ミリリットル入り2750円(税込)で県内外の特約店で取り扱っています。
オリジナルの酒米は、青森県産業技術センター農林総合研究所の協力で開発されました。改良には12年ほど要し、品種の掛け合わせや選抜などを繰り返して2024年度に完成しました。酒米は八戸市蟹沢地区で栽培。今後、酒米を命名し、書類審査や現地調査などを経て、品種の正式登録を目指しています。
駒井庄三郎社長は「こつこつ取り組み、ようやく酒ができるほどのコメが取れた。蔵人が一生懸命、思いを込めた」とPRしています。また、杜氏の駒井伸介常務は「コメは香りと味わいがしっかりとした青森らしい味。記念ボトルは適度な甘みがあるがすっきりキレのあるお酒になった」と話しています。
酒米の開発は、長い年月と多額のコスト、さらに栽培ノウハウの確立といった大きなハードルを伴います。しかし、その過程で生まれる物語性はブランド価値を高め、他銘柄との差別化にもつながります。加えて、地域農家との継続的な協力関係や地元経済への波及効果など、多方面への恩恵も期待できます。今回の八戸酒造の取り組みは、12年にわたる研究・栽培・改良の積み重ねが実を結んだものであり、地域と共に歩む酒蔵の姿勢を象徴する事例と言えるでしょう。
③.400回洗える酒器用ヒノキ升(詳細はコチラ)
海外で日本酒人気が広がる中、普段使いの酒器として木製の升が脚光を浴びています。手掛けているのは岐阜県の金属部品加工の児玉工業所です。木の質感を保ちながら耐水性を高める独自のコーティング技術を採用し、食洗機で繰り返し洗える強度を実現しています。
販路拡大の壁となっていたのが木升の使い勝手の悪さで、木製特有の色移りがしやすく、洗うとシミなどができやすいです。また、使えるのは数回が限度でしかも出荷するまで厳格な温度管理が必要です。実用性を高めたウレタン塗装ではプラスチック製に近いためヒノキの手触りを出しにくく、食洗機で洗うと表面がはがれる懸念もありました。木製の良さを生かしつつ耐久性をどう高めるかを考え、たどりついたのがガラスで表面をコーティングする方法だったそうです。
液体状のガラスを木材に浸透させて塗装すると、木の風合いを保ちながら劣化を防ぐことができます。建材などで使う技術を升に応用し、ヒノキの手触りや香りを損なわず、400回以上洗っても耐えられる強さを実証しました。ガラスを意味する玻璃(はり)を冠して「玻璃塗」というブランドで2024年12月に発売となりました。価格は4180円と一般の升のおよそ10倍です。
価格は一般的な木升の約10倍と高額ですが、ヒノキの手触りや香りを損なわずに400回以上使用できる点は、従来の木升と比べて大幅な利便性向上といえます。ガラスコーティングにより衛生面も確保されるため、飲食店での繰り返し利用はもちろん、木升の扱いになれていない海外市場での活用も期待できます◎
😀8月18日(月)~8/30(土)までカンボジア・プノンペンに訪問します!プチ日本酒イベント、市場調査、お酒の拡販活動、などなど、精力的に活動する予定です!カンボジアにてお会いする予定の皆さま、宜しくお願いします🍶✨