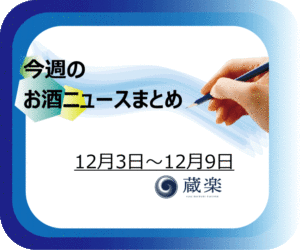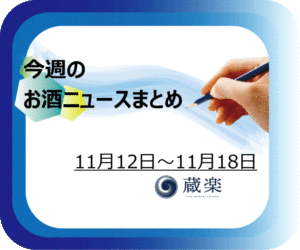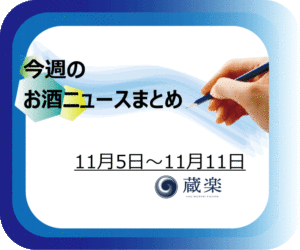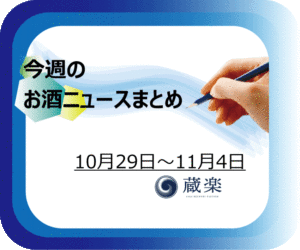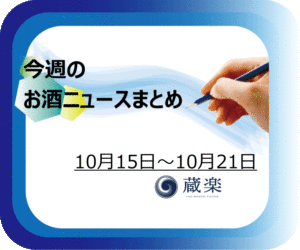おかげさまで株式会社蔵楽は、2025年10月1日に創業5周年を迎えることができました。
節目を記念し、これまでお世話になった皆さまをお招きして、名酒センターさんで「5周年感謝祭」を開催しました。
コロナ禍の創業から5年。
こうして多くの方々と笑顔で集い、お酒を酌み交わしながら語り合える日が来たことに、嬉しく感じました。
お祝いに際して、蔵元の皆さまからたくさんのお酒をお贈りいただき、宇都宮酒造(四季桜)の今井専務にもご来場いただくなど、心温まる時間となりました。
蔵楽は日本酒の東南アジアへの輸出事業や、国内の酒蔵様の経営・販売支援を通じて、業界の発展に取り組んでおります。

次の10年に向けて、引き続き日本酒を中心に人と文化をつなぎ、新たな挑戦を続けてまいります!
今後とも変わらぬご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは今週の日本酒NEWSです🍶✨
🍶トピック🍶
①.笹一酒造 旅の駅とのコラボ日本酒
②.ライスレジンを使用した徳利とお猪口
③.小林順蔵商店のプロジェクト「SAKE INITIE(サケイニシエ)」
①.笹一酒造 旅の駅とのコラボ日本酒(詳細はコチラ)
山梨県の老舗酒蔵、笹一酒造は「笹一 旅の駅 kawaguchiko base Edition」を新たにリリースしました。この限定酒は、富士山のふもとに位置する複合型商業施設「旅の駅 kawaguchiko base」とのコラボレーションによって生まれました。
笹一酒造は、1661年に創業し、富士御坂の透き通った水を使用して日本酒を造り続けています。独自に選定した水と山梨県産の米を使用し、品質を重視した酒造りを行っています。
今回、「富士御坂の恵みを訪れる全ての人へ届けたい」という思いから、笹一酒造と大伴リゾートが手を組みました。これまでにも、先行販売や試飲イベントを行いながら、地元の魅力を発信してきた両者が、この新しい日本酒を通じて更なる地域活性を目指しています。
銘柄のラベルは、アートディレクターである川上シュン氏によってデザインされています。伝統と現代の美が融合した独自のスタイルを持ち、富士山の象徴的な存在を感じさせるものとなっています。味わいは、香り高くまろやかで飲みやすい食中酒となっています。山梨産の甲州山田錦から造られており、すっきりした飲み口と共に優れたクリア感が広がり、清涼感のあるミネラル感も後味にしっかりと留まるそうです。
富士御坂という土地のストーリーと日本酒の魅力がしっかりと結びついた、地域ブランディングの好例といえます。
単なる地産地消にとどまらず、「旅の駅」という観光拠点と連携することで、地域体験そのものを価値に変えている点が特徴的です。
今後は、富士山エリア全体の観光ルートと連動したプロモーション展開にも広がりが期待できますね。
②.ライスレジンを使用した徳利とお猪口(詳細はコチラ)
ミュージックセキュリティーズ株式会社が運営する事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」にて、株式会社ライスレジンの新商品開発を応援するファンドの募集を開始しました。このファンドは、“食用として消費されなかったお米”を原料としたバイオマスプラスチック「ライスレジン」を使用した、お米率(お米の含有率)51%の「徳利とお猪口」の開発を後押しするもので、募集資金は、製品化に必要な金型や初期ロットの製造費、デザイン費などに充てられます。
世界的に環境問題が深刻化する中、石油由来プラスチックの代替素材が求められています。その解決策のひとつとして、日本の主食である「お米」に着目したのがライスレジンです。未利用資源である国産米を活用した環境配慮型素材として注目されています。
原料となるのは、食用として消費されなかった
・古米・破砕米・クズ米などの未利用米
・時間の経過によって食用として扱えなくなった政府備蓄米
・「新市場開拓米制度」を活用して栽培される資源米
などのお米です。
これらを有効活用することで、食品ロス削減と循環型社会の実現に貢献しています。また、ライスレジン用の米づくりは休耕田や耕作放棄地の再利用にもつながり、土壌改良を経て、いずれは食用米の生産に切り替えることも可能です。
完成した酒器は、お土産や贈答品としての展開を視野に入れており、今後は全国の日本酒とのコラボレーションや海外展開も見据えています。
お米の可能性を“食べる”から“使う”へと広げた、循環型ものづくりの好例です。消費されなかったお米を活用し、日本酒の器に生まれ変わらせ。この発想は、日本酒文化の本質である「お米への敬意」を新しい形で表現していると言えますね。
③.小林順蔵商店のプロジェクト「SAKE INITIE(サケイニシエ)」(詳細はコチラ)
大阪を拠点に日本酒の輸出を手がける小林順蔵商店が、世界のワイン市場に向けて新たなプロジェクトを始動しました。「SAKE INITIE(サケイニシエ)」は、日本酒を知らない人に好きになるきっかけを届けるプロジェクトです。
「SAKE INITIE」は、名前に“古(いにしえ)”と“Initie=始まり”を掛け合わせた造語です。欧州を中心に20カ国以上で日本酒を輸出してきた同社が、それらの国の人々の声をもとに構想した新ブランドとなります。スイスやイタリアなどで日本酒の認知度はまだ低く、「強い酒」「読めないラベル」「どれも似ている」という印象を持たれがちで、さらに輸送コストで価格が数倍に跳ね上がり手に取りづらい高級品として扱われているそうです。そのような「文化と言語の壁」を壊し、もっと自由に日本酒を楽しんでもらうために誕生したのが、このブランドとなっています。

第一弾商品「Neo Trad Rabbit(ネオ・トラッド・ラビット)」は、初心者でも一口で“美味しい”と感じる設計を目指してつくられました。アルコール度数は13度と低めで、ラ・フランスのようなフルーティな香りと、白い花を思わせるやわらかな甘みが特徴となっています。また、すっきりとした酸味が全体を引き締め、軽やかな余韻を残します。
小林順蔵商店は、このプロジェクトを応援購入サービス「Makuake」で始動し、国内外から支援を募っています。今後はシリーズ展開を目指し、“飲めば好きになる”をテーマに、世界中のテーブルに新しい日本酒文化を届けていく予定です。
海外のリアルな声から生まれた、まさに“逆輸入型の日本酒改革”ですね。漢字や伝統的意匠をあえて排し、ポップなデザインとワイングラス提供というアプローチは、「文化の壁を越える体験設計」として非常に意義深いです。輸出現場を知る商社だからこそ実現できた、日本酒の新しい入り口づくり。10月15日の公開からわずか10日で目標の2倍以上を達成したことも、その共感の広がりを物語っています。プロジェクトページはこちらから!
😀{当社が行っている日本酒サブスク「TAMEHSHU」ですが、今月のテーマは「ひやおろし特集」です!弥右衛門 純米辛口冷やおろし (福島県 大和川酒造店様) /赤城山 純米ひやおろし(群馬県 近藤酒造 様 )/ 月不見の池 純米吟醸ひやおろし(新潟県 猪又酒造様)の3本を選ばせていただきました!三者三様のおいしさながらも、どれもコクと旨味がのっていて秋の味覚にぴったりでした!🍶✨