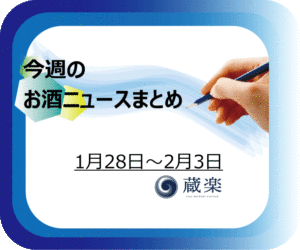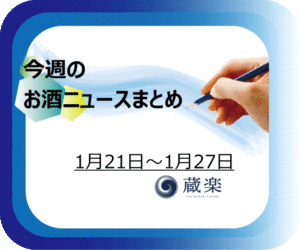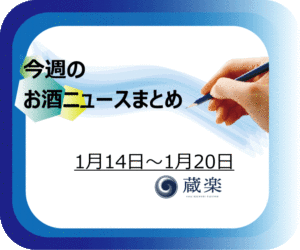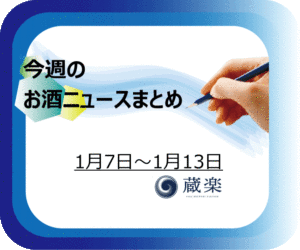Youtubeチャンネル『業界ビジネスチャンネル』の酒ビジネス編の最新版が公開されました!
今回は、米不足について日本酒業界の目線でお話をさせていていただきました。
お米に関してはまだまだ勉強不足な部分もあり、特に流通に対する知識をもっと磨いていきたいと感じました。
次回、第3弾も公開されましたら改めてご報告いたします!
それでは今週の日本酒NEWSです🍶✨
🍶トピック🍶
①.長野県 日本酒で全国1位目指しクラウドファンディング
②.酒米の品質 ドローンで収穫前に把握
③.沢の鶴 データプラットフォームで認知拡大
①.長野県 日本酒で全国1位目指しクラウドファンディング(詳細はコチラ)
長野県は全国新酒鑑評会での金賞受賞数で全国1位になることを目指し、クラウドファンディングを始めました。長野県は5月に開かれた全国新酒鑑評会で金賞受賞数は12品で全国4位でした。
寄付金は県内の酒蔵を対象にした研修会や日本酒の成分分析などに活用され、官民連携で日本酒の品質向上に使われます。
目標額は200万円で、ふるさと納税ではない通常の寄付も可能です。また、5000円以上の寄付者は日本酒の試飲が可能なセミナーに招待されます。
寄付は県が運営するふるさと納税受付サイト「ガチなが」で2026年3月31日まで受け付けています。
(クラウドファンディングのページはこちらから!)
従来の日本酒支援は、特定の酒蔵やブランド単位が中心となりやすい中、このクラウドファンディングは「長野」という広域な県単位取り組みです。参加型の支援・応援であるため、長野ファンも生み出せそうです!品質向上と長野県の日本酒ファンの創出同時に達成できる新しいモデルになるかもしれません。
②.酒米の品質 ドローンで収穫前に把握(詳細はコチラ)
神奈川県・泉橋酒造は稲の収穫作業前に生育状況を把握できる「酒米の予測技術」の特許を出願しました。県立産業技術総合研究所と千葉大学と共同の取り組みで、無人機ドローンと特殊カメラを使い、酒米の品質を判断できるとされるタンパク質含有率を「見える化」しました。
これまでは収穫した酒米のタンパク質などの成分分析は時間や労力がかかる上、一部の水田の酒米しかできず、全体の仕込みの計画に反映できませんでした。そこで、広い水田の状況をくまなく素早く把握できるドローンを活用し、2018年に産技総研と実証実験を開始しました。収穫前に成分が把握できれば、事前に作成している醸造計画を反映させやすく、収穫や仕込みの順番、倉庫の保管場所も決めやすいといいます。
同社の橋場友一社長は「収穫前に仕込みに適した酒米を短時間で選定が可能になる。今後のより良い酒造りにつなげたい」と話しています。
お米の品質管理はお酒の出来映えに直結します。今後、タンパク質含有率だけでなく、心白率・千粒重など、より多くの情報が解像度高く収穫前から「見える化」されれば、酒造りの計画もさらにスムーズになりそうです。
③.沢の鶴 データプラットフォームで認知拡大(詳細はコチラ)
沢の鶴株式会社とアライドアーキテクツ株式会社は、日本酒「SHUSHU Light」のパッケージリニューアルに伴う若い世代への認知拡大施策を支援いたしました。
同酒造は、2021年に発売した「SHUSHU Light」のパッケージデザインのリニューアルを機に、20-30代の若い世代への認知拡大を図りたいと考えていました。
そこで今回、”顧客の声”をAIで解析し、コミュニケーションの”起点となるインサイト”を発見し続けるデータプラットフォーム「Kaname.ax」を導入。分析結果に基づいて、若い世代をターゲットにしたモニター施策を実施しました。
沢の鶴株式会社マーケティング室の矢野課長は、「今回のプロモーションでの大きな成果は、利用シーンの訴求に成功したことです。強化したいと考えていた「休日の昼間に飲む」「週末・休日に飲む」といったカテゴリーエントリーポイントにしっかりとマッチしており、非常に質の高いUGC(※)の創出に繋がりました」とコメントしています。
※UGC・・・user-generated content:エンドユーザーの手によって作成されたコンテンツの総称のこと
20-30代の若い世代が利用するSNSでのお酒投稿をAIで分析し、「実際にどのようにお酒が飲まれてきたのか」の実証が可能となりました。AIによるマーケティング活用方法は着実に進んできていますね。
😀いよいよ本日からカンボジア入りです!来週以降アップデート情報もメルマガにて配信をさせていただきます!お楽しみに!🍶✨