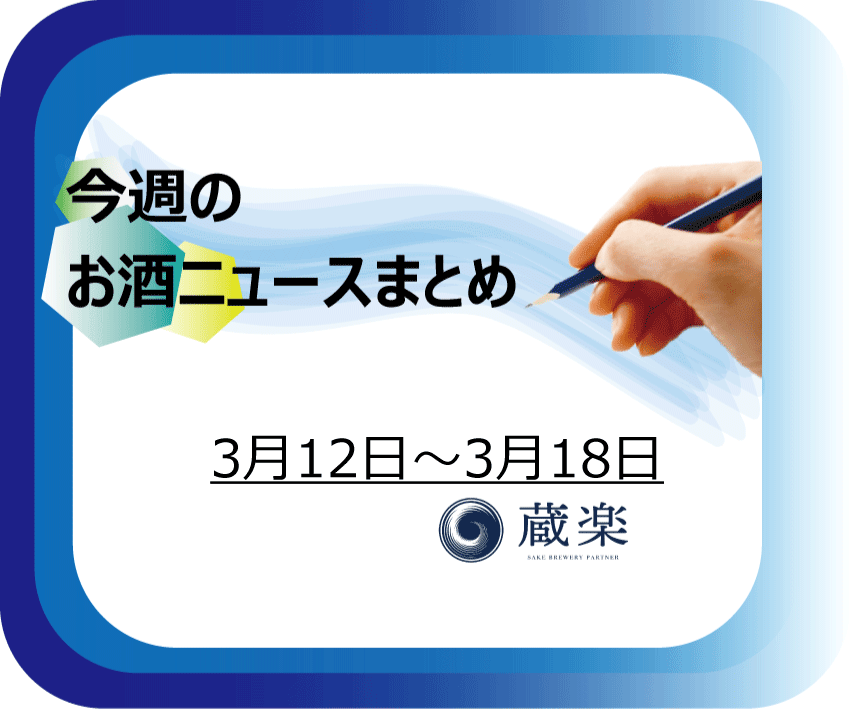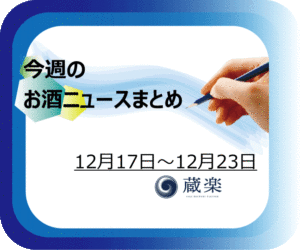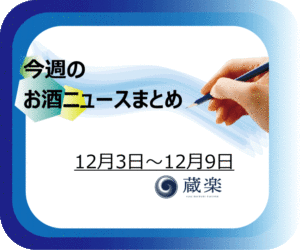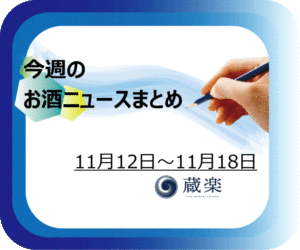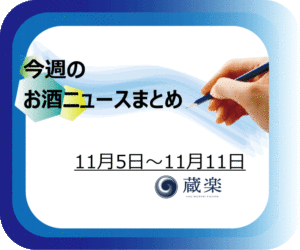先日、第1回となる、海外SAKEビジネス勉強会を開催しました。
海外のSAKEビジネスを携わる方を約20名集めて、意見交換を実施しました。
カンボジアで日本酒の普及活動を行っており、一定の成果は出てきたものの、我流でやっている部分もあるため、他の方がどうされているのが非常に気になっていました。
そんな中で、オーストラリアで活躍するのジャムズジャパン株式会社の遠藤烈士さんに連絡をしたところ、「勉強会をやってみよう!」という話になり、無事に実現に至りました。
アメリカ、インド、イギリス、オーストラリアと世界各国で活躍される方が、一堂に会することができました。
当日は、熱量のあるディスカッションができ、懇親会を含めてあっという間でした!
皆さんとの意見交換を通じて、まだまだやれることは沢山あると思いました。
今後も、カンボジア含めて東南アジアマーケットをしっかりと広げていければと思います!
それでは今週の日本酒NEWSです🍶✨
🍶トピック🍶
➀.日本酒国内向け製造 新規免許「70年ゼロ」 世界のSAKEブームに逆行
②.八海醸造、ドジャースとパートナー契約 公式日本酒に
③.きき酒を目指す外国人が増加 台湾から来日し酒蔵見学
➀.日本酒国内向け製造 新規免許「70年ゼロ」 世界のSAKEブームに逆行 (詳細はコチラ)
日本酒業界では、国内向け製造の新規免許を認めないルールが70年にわたり続いています。既存酒蔵の保護を優先する一方で、国内市場はピーク時の5分の1まで縮小しました。日本食人気とともに世界にSAKEの名が広まり、輸出は増加傾向にあるなか、日本酒業界の製造免許制度の刷新が求められています。
新規参入者は免許取得のために既存事業者をM&A(合併・買収)するしかなく、多額の負債を引き受けるリスクが伴います。さらに、酒蔵に醸造を委託する「ファントムブルワリー」という方法もありますが、委託費を商品価格に上乗せする必要があり、コストが割高で参入障壁は依然として高い状況です。
2021年には輸出限定の製造免許が設けられ、7社が参入しましたが、国内市場でのブランド力の構築が難しく、輸出拡大の妨げになっているとの声もあります。23年には男鹿市と稲とアガベが新規参入を認める国家戦略特区を正式申請しましたが、既存の酒蔵経営の厳しさを訴え、伝統を重視する秋田県酒造協同組合との溝は埋まらず、清酒免許に関する動きは停滞しています。
一方で、ビール業界では1994年の規制緩和により製造免許の最低製造量が年間2000キロリットルから60キロリットルに引き下げられ、「マイクロブルワリー」が各地で誕生しました。発泡酒はさらに参入障壁が低く、6キロリットルから製造が可能です。
規制緩和で先行したビール、発泡酒は「地ビール」や「クラフトビール」ブームを生み、大手メーカーとは異なる新たなファン層を開拓しています。日本酒も近年、新進気鋭の造り手が登場し、その個性を競っています。市場が縮小傾向にあるからこそ、新陳代謝の促進が必要ではないでしょうか。
米国などでは日本企業以外のSAKE造りが進んでいます。AKEブームに乗り遅れないためにも、守りだけでなく攻めの姿勢も取る必要があるのではないでしょうか。
②.八海醸造、ドジャースとパートナー契約 公式日本酒に(詳細はコチラ)
八海醸造(新潟県南魚沼市)は、米大リーグのドジャースとパートナーシップ契約を締結したと発表しました。
同チームには大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らが所属しており、契約期間は3月からの2年間で、同期間中は「八海山」がドジャースの公式日本酒となります。
シーズン中はドジャースの本拠地であるドジャースタジアムでしか手に入らないオリジナルカップでの販売や、スタジアムに設置されているモニターにデジタル広告の掲出などを予定しており、「八海山」が楽しめる来場者向けの体験イベントも計画しています。
今回のパートナーシップ契約に関してはドジャース側から依頼での案件であり、八海醸造の南雲二郎社長は「歴史あるチームとともに、日本酒の可能性を世界に広げていけることを大変光栄に思い、心からワクワクしている。『SAKEを世界飲料に』という夢の実現に向け、ドジャースとのパートナーシップは大きな一歩だ」と話しています。
ドジャースのさらなる活躍とともに、八海山が世界に名を広めることに期待です◎
③.きき酒を目指す外国人が増加 台湾から来日し酒蔵見学 (詳細はコチラ)
近年、日本酒人気の高まりを受け、“きき酒師”を目指す外国人が増えています。先週、台湾で日本酒を学ぶ人たちが来日し、笹祝酒造(新潟市西蒲区)を見学しました。
台湾で日本酒を学んでいる24人が訪れ、塩麹作りを体験しました。 笹祝酒造は普段から塩麹・醤油麹ワークショップを行う「麹の教室」を運営しており、麹の技術と日本酒を次世代につなげるため、誰もが気軽に麹の世界を学べる場を提供しています。
台湾においても、日本酒はどの料理でも相性がいいという評判があるそうです。 参加者からは、日本国内で日本酒を楽しむ体験ができたと声が上がっていました。
参加者は、日本酒のソムリエと言われる“きき酒師”の資格取得を目指しているということです。
日本酒を目当てに来日する人が増え、各地の酒蔵の訪問を通じて地方の良さを知ってもらえたらいいですね!
😀{そろそろ桜が開花しそうですね🌸人の多い名所ではなく、ぶらぶら歩きながら見つけた桜を愛でるのが個人で気には好きです🍶✨