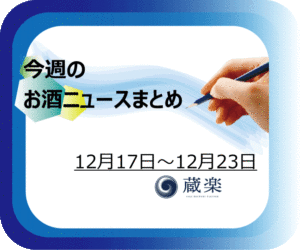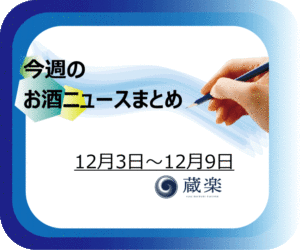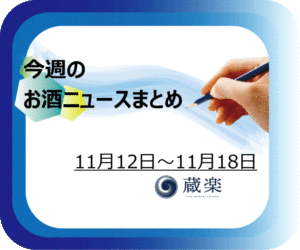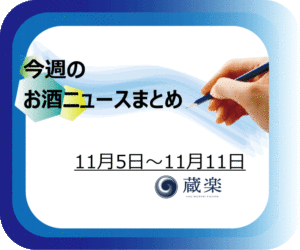お知らせしました『業界ビジネスチャンネル』ですが、大きな反響をいただきました!
そして先週に引き続き最新版が公開されました!今回は、「八海山(八海醸造さん)」についてお話をさせていていただきました。
「日本酒×ビジネス」というと、獺祭さんがフォーカスされがちですが、アルコール業界全体としての八海山のすごさについて、私なりの目線でお話をしております。是非ともご覧いただけますと幸いです◎
それでは今週の日本酒NEWSです🍶✨
🍶トピック🍶
①.日本酒の販売戦略に学生の知恵
②.日本酒を蒸留した「浄酎」 能登の酒造が8月末販売
③.焙煎米麹を使ったスパークリング日本酒
①.日本酒の販売戦略に学生の知恵(詳細はコチラ)
末廣酒造(会津若松市)は、武蔵野大(東京都)の学生と連携し、新たな商品や事業を考えるプロジェクトを展開しています。
プロジェクトに参加する学生が21日、同酒造嘉永蔵を訪れ、2カ月かけて練り上げた「若者をターゲットにした日本酒の販売戦略」を発表しました。発表会では、学生約70人を対象としたアンケートを基にした計画案が披露されました。「日本酒をもっと飲むようになる理由」を聞いた質問では、「甘いものがあったら」「割れるようになったら」「度数が低いものがあったら」が上位に入ったことから、学生たちはこれらの回答を参考にさまざまなアイデアを出しました。
このうち、優勝した班は
・日本酒のパッケージを変更
・貼っているQRコードをさらに大きくして目立たせる
・LINEに誘導した後にリピーターを獲得するためクーポンを発行
・インフルエンサーに告知を依頼
という案を発表しました。学生が考えた各計画は今後、同酒造内で実現可能かどうか検討される予定です。新城大輝社長は「学生の発表には細かい分析と柔軟な発想があった。どの班も素晴らしい案。対応できるのか社内で検討したい」と話しています。
次世代の消費者と会話をすることで。既存概念の枠組みを越えられるかもしれない貴重な機会ですね。
今回のアイデアが具体的にビジネスの場に採用をされるかもしれず、楽しみです!
②.日本酒を蒸留した「浄酎」 能登の酒造が8月末販売(詳細はコチラ)
酒造スタートアップのナオライ(広島県呉市)の子会社、NOTO Naorai(ノトナオライ、石川県中能登町)は、日本酒を蒸留してつくる「浄酎(じょうちゅう)」の販売を8月末に始めます。酒の生産・販売を通じ地震で被災した能登半島の再生に寄与します。21日にお披露目会を開き、ナオライの三宅紘一郎代表やノトナオライに出資する関係者らが出席しました。
同社の浄酎は、能登半島地震の被害を受けた鳥屋酒造の日本酒を低温で蒸留して生産します。日本酒のような香りとウイスキーに似た飲み口が特徴です。北国フィナンシャルホールディングス傘下で投資を手掛けるQRインベストメントなどが設立した「のとBeyond復興ファンド」が、第1号案件として出資しています。また、クラウドファンディングサイト「きびだんご」で取り扱いを始め、今後は金沢市内のレストランなど国内外に販路を拡大しながら一般販売も検討しています。三宅代表は「浄酎を飲めば飲むほど、能登の地域や酒文化が再生していくようなモデルをつくりたい」と展望を語っています。
浄酎は日本酒を40℃以下の低い温度で蒸留して造るもので、アルコール度数は日本酒よりも25度ほど高い41度になります!①浄酎に触れることによる飲み手の新しい味わいの体験、②浄酎そのものの知名度向上や市場拡大、③能登地域への復興寄与、と「三方よし」となるモデルになりそうですね。
③.焙煎米麹を使ったスパークリング日本酒(詳細はコチラ)
Hirose Sake Works(愛知県碧南市)は、焙煎した米麹を使ったスパークリング日本酒「eight焙煎麹スタウト Sparkling」シリーズ3商品を、2025年7月に発売しました。
Hirose Sake Worksは、醸造場所を持たない“ファントムブルワリー”として、日本酒ブランド「eight」を企画・販売しています。今夏発売したのは、米麹を直火焙煎した焙煎麹を使ったスパークリング日本酒です。岐阜県・中島醸造の3種類の日本酒をベースに、焙煎麹酛を添加して、二次発酵させたお酒です。
焙煎麹酛を立てるにあたり、浅煎りと深煎りの米麹、それぞれから生まれる風味や、焙煎麹を浸漬した時と焙煎麹を醪に投入していっしょに発酵させた時の風味の違いを比較したりと、さまざまな検証を重ねて、今回の商品が完成しています。米麹を焙煎することで、一般的な日本酒にはないカカオやチョコレートのようなニュアンスも感じられるそうです。焙煎麹酛の酵母には、白ワイン酵母を使用しています。酵母由来の果実的な酸味が、焙煎の
米麹そのものを焙煎するというアプローチはまるでクラフトサケのようですが、原材料は米と米麹のままであり、酒税法上の「清酒」の範囲を保ったまま新しい味わい表現を行っています。海外展開や若年層の開拓で求められる一つは「新しい体験」ですが、同時に“日本酒としての正統性”を失なっていないことも重要です。日本酒という枠組みを押し広げる切り口になりそうです!
😀{食ビジネスの第一線が集結する「日本の食ビジネス カンファレンス 2025」が9月5日(金)に東京・田町で開催されます!魚・肉・野菜・米・酒、5ジャンルの著者が集まり、日本の食の未来について議論をします。私も登壇をさせていただきますので、是非お近くの方は足を運んでいただければ幸いです!🍶✨